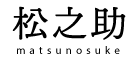エッセイ
ESSAY
ESSAY


Ⅰ 主婦が見た夢
1.アメリカ留学の夢
2.イリノイへの招待
3.幻の留学
4.私への投資は800万円
5.英語との格闘はじまる
6.多国籍クラスのなかで
7.地下のキッチンでの日本食
8.作文が教科書に掲載される
9.若いころもっと本を読んでいれば
10.中国人留学生の死
11.アメリカ式ストレス解消法
12.ようやく正規の大学生として
13.自立するアメリカの学生
14.ドライブ・デビュー
15.驚異のシルバーパワー
16.ニューヨークへひとっ飛び
17.大陸横断旅行
Ⅱ アメリカンケーキへの道
18.アメリカン・ケーキとの出会い
19.おしかけて、弟子入り
20.グレート・アメリカンケーキへの道
21.グレート・アメリカン・アップル・パイの
作り方のポイント
22.セカンド・イズ・ザ・ベスト
23.ベースボールとアメリカン・ケーキ
24.歴史で味わうケーキ作り
25.未知のケーキとの遭遇(1)
26.未知のケーキとの遭遇(2)
27.卒業
28.遅すぎることはない
29.あとがき
5
英語との格闘はじまる
アメリカの大学は、9月が入学のシーズンだが、語学力に不安のある外国からの入学者は、その前に英語に慣れ親しみ、授業をきちんと聞けるようにするために、ELSに入らなくてはならない。私もまずELSに入学することになった。そこで余裕があれば、同時にアカデミックな授業もとっていいですよということだった。その授業は、その後正式に大学に入学したときに、単位として加算されることになっていた。
ELSの授業がはじまるのに合わせ、私は1月半ばに日本を発つことになった。私は、昔からどこに行くのにも荷物が多い。今回の留学も、引越しをするような感じだった。娘だけが見送りに着てくれて、「じゃ、行ってくるわね」と簡単だった。心の中では不安だなあという思いだったが、もちろんそんなのは、顔にださなかった。
日本とはしばらくお別れか、と思うと少々感傷的になったが、ノースウエスト航空の搭乗口に向かうときは、「行ってきまーす」と、学生気分も高まってきた。費用をできるだけ低く抑えるため、少々遠回りになるが、成田からデトロイトに向かい、そこから国内線に乗り換えて、コネチカット州の州都ハートフォードにある、ブラッドリー国際空港という小さな空港に着くことになっていた。
大学は、ストゥルスという地図にも載っていない小さな町にある。もちろん、だれひとり知り合いはいない。異国で暮らす不安が空港に近づくにつれて頭をもたげたが、懸命にそれを振り払い、「どうにかなるさ」と自分で自分を勇気づけた。
飛行機が遅れたため、その田舎の小さな空港に着いたときは夜の11時を回っていた。心もとない。人もまばらで、1月半ばだから学生もいない。ストゥルスの町は、空港からさらに来るまで3、40分かかるというので、この日は大学側に頼んでおいたシャトルバスが私を迎えに来てくれているはずだった。が、私のような留学生らしき人間はだれもいない。英語が通じるかどうかの不安もさることながら、こんなところで夜を明かすことになったらどうしよう、という不安で心臓の鼓動が全身に伝わるようだった。
空港の玄関先に大きな荷物をおいて、とにかく迎えが来るのを信じて待っていた。そのうち、「ホライズン・シャトル」という手書きの看板を持った黒人の青年が近づいてきて、私の名前らしき言葉を言ったので、「イエス」と答えた。でも、この青年を信用していいものかどうか。年をとるとだんだん疑い深くなる。そんな私の心配をよそに、彼はさっさと私の荷物をワゴン車に乗せている。こうなったら彼を信じるしかない。
というもの、車に乗り込んだものの一行に出発しようとしない。ああ、どうしよう。こうなるとネガティブな方へと考えは進んでいく。「中年日本女性アメリカで行方不明」なんて見出しで日本の新聞に載ったらどうしよう。日本人は若く見られるから、私でも30代に見られるかも知れない。彼が人身売買の手先か何かで、私をマフィアに売り飛ばしたら・・・・、ああ、もう二度と子供たちにも会えなくなる。心なしか、足が震えるのを感じ、手のひらにはあぶら汗がにじんできた。
その時、彼が言った。「もうひとり、拾っていかなくてはならないので、もう少し待っててください」 はっきりと彼の言葉が理解できた。スーッと汗がひくのを感じ、ほっとしてシートに座り直した。それまで緊張していてわからなかったが、初めて外が相当寒いことを感じた。しばらくすると、もう1人の留学生が車に乗り込んできた。イタリア人だという彼は、にっこり笑って握手を求めてきたのであわてて手を差しのべた。大げさだが、私にしてみれば、初めての国際親善の瞬間だった。
車が走り出すと窓の外は、暗闇ばかりで景色はなにも見えない。とんでもない田舎だなという印象だった。なんだか真っ暗で、これからの人生を暗示しているみたいだな、などと気が弱くなってしまった。30分くらい走っただろうか、イタリアの留学生のアパートについた。彼は大学のキャンパスの外にあるアパートを借りることになっているらしかった。「シー・ユー」と、片手を上げて彼は建物のなかに消えていった。それから10分ほどしていよいよキャンパス内である。
4階建ての建物は明かりが煌々とともっていた。そこで出迎えてくれたのがアルバイトで、事務所の仕事を手伝っているという大学生だった。彼は、その建物の3階にある302号室に私を案内し、荷物を入れてくれた。私は、また1階までもどり、入居のサインをして鍵を2個受け取って部屋に戻った。気温が摂氏0度以下だと気がついたのはこのときだった。
幸い室内はセントラルヒーターがよくきき暖かかった。8畳ほどの部屋にベッド、洋服ダンスも置いてある。が、そこで、はたと気がついた。枕も布団もないのである。夜中だしどうしようもない。やはり、アメリカは大ざっぱなのか。仕方がないので、ボストンバッグからバスタオルを出して枕をつくり、オーバーを布団代わりにベッドに横になった。
どっと、疲れが襲ってきたがなかなか寝付けない。音がないということがこんなにも、寂しいものだとは知らなかった。体を丸めて、ベッドサイドの壁をじっと眺めながら思わす言葉が口をついて出てきた。「思えば遠くへ来たもんだ」 成田から飛行機を乗り継いで16時間。こうして私の留学生活の初日は終った。日本を出発した日とまた同じ日の朝を迎えようとしていた。
ELSの授業がはじまるのに合わせ、私は1月半ばに日本を発つことになった。私は、昔からどこに行くのにも荷物が多い。今回の留学も、引越しをするような感じだった。娘だけが見送りに着てくれて、「じゃ、行ってくるわね」と簡単だった。心の中では不安だなあという思いだったが、もちろんそんなのは、顔にださなかった。
日本とはしばらくお別れか、と思うと少々感傷的になったが、ノースウエスト航空の搭乗口に向かうときは、「行ってきまーす」と、学生気分も高まってきた。費用をできるだけ低く抑えるため、少々遠回りになるが、成田からデトロイトに向かい、そこから国内線に乗り換えて、コネチカット州の州都ハートフォードにある、ブラッドリー国際空港という小さな空港に着くことになっていた。
大学は、ストゥルスという地図にも載っていない小さな町にある。もちろん、だれひとり知り合いはいない。異国で暮らす不安が空港に近づくにつれて頭をもたげたが、懸命にそれを振り払い、「どうにかなるさ」と自分で自分を勇気づけた。
飛行機が遅れたため、その田舎の小さな空港に着いたときは夜の11時を回っていた。心もとない。人もまばらで、1月半ばだから学生もいない。ストゥルスの町は、空港からさらに来るまで3、40分かかるというので、この日は大学側に頼んでおいたシャトルバスが私を迎えに来てくれているはずだった。が、私のような留学生らしき人間はだれもいない。英語が通じるかどうかの不安もさることながら、こんなところで夜を明かすことになったらどうしよう、という不安で心臓の鼓動が全身に伝わるようだった。
空港の玄関先に大きな荷物をおいて、とにかく迎えが来るのを信じて待っていた。そのうち、「ホライズン・シャトル」という手書きの看板を持った黒人の青年が近づいてきて、私の名前らしき言葉を言ったので、「イエス」と答えた。でも、この青年を信用していいものかどうか。年をとるとだんだん疑い深くなる。そんな私の心配をよそに、彼はさっさと私の荷物をワゴン車に乗せている。こうなったら彼を信じるしかない。
というもの、車に乗り込んだものの一行に出発しようとしない。ああ、どうしよう。こうなるとネガティブな方へと考えは進んでいく。「中年日本女性アメリカで行方不明」なんて見出しで日本の新聞に載ったらどうしよう。日本人は若く見られるから、私でも30代に見られるかも知れない。彼が人身売買の手先か何かで、私をマフィアに売り飛ばしたら・・・・、ああ、もう二度と子供たちにも会えなくなる。心なしか、足が震えるのを感じ、手のひらにはあぶら汗がにじんできた。
その時、彼が言った。「もうひとり、拾っていかなくてはならないので、もう少し待っててください」 はっきりと彼の言葉が理解できた。スーッと汗がひくのを感じ、ほっとしてシートに座り直した。それまで緊張していてわからなかったが、初めて外が相当寒いことを感じた。しばらくすると、もう1人の留学生が車に乗り込んできた。イタリア人だという彼は、にっこり笑って握手を求めてきたのであわてて手を差しのべた。大げさだが、私にしてみれば、初めての国際親善の瞬間だった。
車が走り出すと窓の外は、暗闇ばかりで景色はなにも見えない。とんでもない田舎だなという印象だった。なんだか真っ暗で、これからの人生を暗示しているみたいだな、などと気が弱くなってしまった。30分くらい走っただろうか、イタリアの留学生のアパートについた。彼は大学のキャンパスの外にあるアパートを借りることになっているらしかった。「シー・ユー」と、片手を上げて彼は建物のなかに消えていった。それから10分ほどしていよいよキャンパス内である。
4階建ての建物は明かりが煌々とともっていた。そこで出迎えてくれたのがアルバイトで、事務所の仕事を手伝っているという大学生だった。彼は、その建物の3階にある302号室に私を案内し、荷物を入れてくれた。私は、また1階までもどり、入居のサインをして鍵を2個受け取って部屋に戻った。気温が摂氏0度以下だと気がついたのはこのときだった。
幸い室内はセントラルヒーターがよくきき暖かかった。8畳ほどの部屋にベッド、洋服ダンスも置いてある。が、そこで、はたと気がついた。枕も布団もないのである。夜中だしどうしようもない。やはり、アメリカは大ざっぱなのか。仕方がないので、ボストンバッグからバスタオルを出して枕をつくり、オーバーを布団代わりにベッドに横になった。
どっと、疲れが襲ってきたがなかなか寝付けない。音がないということがこんなにも、寂しいものだとは知らなかった。体を丸めて、ベッドサイドの壁をじっと眺めながら思わす言葉が口をついて出てきた。「思えば遠くへ来たもんだ」 成田から飛行機を乗り継いで16時間。こうして私の留学生活の初日は終った。日本を出発した日とまた同じ日の朝を迎えようとしていた。