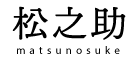エッセイ
ESSAY
ESSAY


Ⅰ 主婦が見た夢
1.アメリカ留学の夢
2.イリノイへの招待
3.幻の留学
4.私への投資は800万円
5.英語との格闘はじまる
6.多国籍クラスのなかで
7.地下のキッチンでの日本食
8.作文が教科書に掲載される
9.若いころもっと本を読んでいれば
10.中国人留学生の死
11.アメリカ式ストレス解消法
12.ようやく正規の大学生として
13.自立するアメリカの学生
14.ドライブ・デビュー
15.驚異のシルバーパワー
16.ニューヨークへひとっ飛び
17.大陸横断旅行
Ⅱ アメリカンケーキへの道
18.アメリカン・ケーキとの出会い
19.おしかけて、弟子入り
20.グレート・アメリカンケーキへの道
21.グレート・アメリカン・アップル・パイの
作り方のポイント
22.セカンド・イズ・ザ・ベスト
23.ベースボールとアメリカン・ケーキ
24.歴史で味わうケーキ作り
25.未知のケーキとの遭遇(1)
26.未知のケーキとの遭遇(2)
27.卒業
28.遅すぎることはない
29.あとがき
27
卒業
1998年春。勢いだけで、アメリカに来てから2年3ヶ月が過ぎていた。
最後の試験が終わった時点で、私には卒業できることが分かった。とうとう終わったのだ。そうはっきりわかってから、私は日本の家族に連絡した。
記念すべき5月24日の卒業式には、男も女も黒の四角いハットとガウンを着ることになっている。夢にまで見た姿である。でも、実際にガウンを手にしてみると、化繊のペラペラしたちゃちなものだとわかって、ちょっとがっかり。これは25ドルで買うことになっていいて、結構高いななんて思った。しかし、あのハットだけは憧れだった。だから、どんなふうにかぶろうかなあ、と卒業式まではあれこれ考えて年甲斐もなくワクワクしていた。
そして、卒業式。コネチカットの気候というのは、あてにならなくて、4月でも雪がふるし、初夏でも真夏のような暑さになるときもあった。この年の卒業式の日は、夏の一歩手前という感じの日で、ものすごく暑かった。黒いガウンを着て、屋外での式だったから、暑いのなんの。校長先生の話は長いし、そのへんは日本と変わらなかった。違うところは式自体は、それほど厳粛ではないところだ。
卒業生は、代表者だけが壇上に上がるのではなく、一人ひとりが壇に上がって、校長先生と握手して、終了証書が読まれる手はずになっていた。そこで、呼ばれた名前が知人や友人の名前だとわかると、「ヒュー」といった奇声があがり、雰囲気が盛り上がる。めそめそするより喜びでいっぱいなのだ。
卒業できる喜びは私にもあった。けれど、その時の気持ちは「感動」とはまたちょっと違ったものだった。私の名前が呼ばれ、終了証書を手にしたあとで胸にこみ上げてきたのは、「あー、これで娘には快挙を成し遂げたといえるし、息子からは良くやったっていわれるだろうな」という安心感と充足感だったと思う。ほっとしたという気持ちがある。「嬉しさ」という点では、なによりも、「自分はいま勉強しているんだなあ」と、実感していたときのほうが嬉しかった。つらかったけれど、ほんとうにうれしかった。
自分ではそれほど大変なことをしたとは思わなかったけれど、日本に帰ってきてから、「良く卒業できたわね、その年齢で」と、言われることが多かったが、その方がむしろ驚きだった。そんなに大変だったのかなと。
もちろん私にしては大変だった。けれども、正直に言えば、中年で勉強しに来ていた私に対して、先生方が甘く見てくれたところもあったと思う。もし、1つでも単位を落とせば、またサマーセッションで試験を受けて合格しなくてはならない。そして、もし、その科目が夏になくて、秋からの学期の授業に出なくてはならないとしたら、私は続けられたかどうかわからななかった。だから必死ですべての教科の先生に対して、「この歳で外国から来たので、なんとか卒業したいと思います。がんばりますのでよろしくお願いします」と、言い続けてきた。それで、どうなったかはわからないけれど、少しは印象に残っていたと思う。
当初の予定では私は、卒業式の日に帰国する予定だった。だが、5月30日にハートフォードにある全米で一番古い美術館で大晩餐会が開かれることになり、幸運にも私も参加することになったのである。私の先生が会の料理人に選ばれ、私に助手になってくれというのだ。これも滅多になりチャンスである。私は二つ返事でOKし、その日が終わるまで、帰国を延ばした。
晩餐会には名士たち約200人が招待され、食事のあとに芸術を鑑賞するという贅沢な試みだった。コネチカットの有名なレストランのシェフや、料理学校の先生、もちろんお菓子の関係者も集まったので、見ているだけでも勉強になる。
そして、その晩餐会が終わると同時に帰国の途についた。帰国してからのことを考えると、不安はあった。でも、最後に先生が、 「自信を持ってやれば大丈夫」と、背中を押してくれ、励ましてくれた。アメリカのケーキばベーシックなケーキ作りの方法を学ぶことである。だから、子供でも男性でも手軽に挑戦できる。
「よし、帰ったらこれでなんとか身を立てていこう」
そう思ってコネチカットをあとにした。
最後の試験が終わった時点で、私には卒業できることが分かった。とうとう終わったのだ。そうはっきりわかってから、私は日本の家族に連絡した。
記念すべき5月24日の卒業式には、男も女も黒の四角いハットとガウンを着ることになっている。夢にまで見た姿である。でも、実際にガウンを手にしてみると、化繊のペラペラしたちゃちなものだとわかって、ちょっとがっかり。これは25ドルで買うことになっていいて、結構高いななんて思った。しかし、あのハットだけは憧れだった。だから、どんなふうにかぶろうかなあ、と卒業式まではあれこれ考えて年甲斐もなくワクワクしていた。
そして、卒業式。コネチカットの気候というのは、あてにならなくて、4月でも雪がふるし、初夏でも真夏のような暑さになるときもあった。この年の卒業式の日は、夏の一歩手前という感じの日で、ものすごく暑かった。黒いガウンを着て、屋外での式だったから、暑いのなんの。校長先生の話は長いし、そのへんは日本と変わらなかった。違うところは式自体は、それほど厳粛ではないところだ。
卒業生は、代表者だけが壇上に上がるのではなく、一人ひとりが壇に上がって、校長先生と握手して、終了証書が読まれる手はずになっていた。そこで、呼ばれた名前が知人や友人の名前だとわかると、「ヒュー」といった奇声があがり、雰囲気が盛り上がる。めそめそするより喜びでいっぱいなのだ。
卒業できる喜びは私にもあった。けれど、その時の気持ちは「感動」とはまたちょっと違ったものだった。私の名前が呼ばれ、終了証書を手にしたあとで胸にこみ上げてきたのは、「あー、これで娘には快挙を成し遂げたといえるし、息子からは良くやったっていわれるだろうな」という安心感と充足感だったと思う。ほっとしたという気持ちがある。「嬉しさ」という点では、なによりも、「自分はいま勉強しているんだなあ」と、実感していたときのほうが嬉しかった。つらかったけれど、ほんとうにうれしかった。
自分ではそれほど大変なことをしたとは思わなかったけれど、日本に帰ってきてから、「良く卒業できたわね、その年齢で」と、言われることが多かったが、その方がむしろ驚きだった。そんなに大変だったのかなと。
もちろん私にしては大変だった。けれども、正直に言えば、中年で勉強しに来ていた私に対して、先生方が甘く見てくれたところもあったと思う。もし、1つでも単位を落とせば、またサマーセッションで試験を受けて合格しなくてはならない。そして、もし、その科目が夏になくて、秋からの学期の授業に出なくてはならないとしたら、私は続けられたかどうかわからななかった。だから必死ですべての教科の先生に対して、「この歳で外国から来たので、なんとか卒業したいと思います。がんばりますのでよろしくお願いします」と、言い続けてきた。それで、どうなったかはわからないけれど、少しは印象に残っていたと思う。
当初の予定では私は、卒業式の日に帰国する予定だった。だが、5月30日にハートフォードにある全米で一番古い美術館で大晩餐会が開かれることになり、幸運にも私も参加することになったのである。私の先生が会の料理人に選ばれ、私に助手になってくれというのだ。これも滅多になりチャンスである。私は二つ返事でOKし、その日が終わるまで、帰国を延ばした。
晩餐会には名士たち約200人が招待され、食事のあとに芸術を鑑賞するという贅沢な試みだった。コネチカットの有名なレストランのシェフや、料理学校の先生、もちろんお菓子の関係者も集まったので、見ているだけでも勉強になる。
そして、その晩餐会が終わると同時に帰国の途についた。帰国してからのことを考えると、不安はあった。でも、最後に先生が、 「自信を持ってやれば大丈夫」と、背中を押してくれ、励ましてくれた。アメリカのケーキばベーシックなケーキ作りの方法を学ぶことである。だから、子供でも男性でも手軽に挑戦できる。
「よし、帰ったらこれでなんとか身を立てていこう」
そう思ってコネチカットをあとにした。