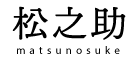エッセイ
ESSAY
ESSAY


Ⅰ 主婦が見た夢
1.アメリカ留学の夢
2.イリノイへの招待
3.幻の留学
4.私への投資は800万円
5.英語との格闘はじまる
6.多国籍クラスのなかで
7.地下のキッチンでの日本食
8.作文が教科書に掲載される
9.若いころもっと本を読んでいれば
10.中国人留学生の死
11.アメリカ式ストレス解消法
12.ようやく正規の大学生として
13.自立するアメリカの学生
14.ドライブ・デビュー
15.驚異のシルバーパワー
16.ニューヨークへひとっ飛び
17.大陸横断旅行
Ⅱ アメリカンケーキへの道
18.アメリカン・ケーキとの出会い
19.おしかけて、弟子入り
20.グレート・アメリカンケーキへの道
21.グレート・アメリカン・アップル・パイの
作り方のポイント
22.セカンド・イズ・ザ・ベスト
23.ベースボールとアメリカン・ケーキ
24.歴史で味わうケーキ作り
25.未知のケーキとの遭遇(1)
26.未知のケーキとの遭遇(2)
27.卒業
28.遅すぎることはない
29.あとがき
8
作文が教科書に掲載される
夕食後は、みなそれぞれの部屋へ戻る。私は、予習、復習は最低5時間はやっていた。日付が変わっても寝られないこともしばしばだった。それでも、5時間やっていても、進んでいるというよりは、むしろ後退している感じがしたほどだ。それほど、やらなくてはならないことは多かった。ELSの授業はかならず宿題がでる。それをこなして、なんとかついていけるくらいだった。
また、私はELSの授業のほかに、春や夏に短期で行われる講座の授業も少しとっていた。ここでは、宿題はでないが、これも予習していかないと授業にはついていけず、勉強時間の配分がむずかしかった。
一般の講座はアメリカ人を対象にしているので、もちろん若い学生ばかり。自分の息子と娘と同じ世代ばかりである。そのなかで私のような中年の、まして外国人の女性となるとひとりだけ。当たり前だろう。「あ、おばさんが日本から来ているんだな。どういう理由で来ているのかな」といった感想をもっていたとは思う。でも、決して好奇の目でみるようなことはなかった。よっぽど親しくなった学生が、いろいろ聞いてくるので、私は正直に答えた。
「歳はいくつ?」
「女の人に歳を聞くもんじゃないわよ」
「お母さんくらいかな」
「そう、あなたのお母さんくらいかな」
「ふーん、どうして大学にきているの」
「昔からの夢で、アメリカの大学卒業したかったから」
「えらいねー、うちのお母さんにも言ってやろう」
なんていう話になる。でも、それ以上にあれこれ聞いてくることはない。歳も離れているから、学校外でのつきあいというのはほとんどない。とはいっても、少しは親しい友だちをつくっておかないと、授業のことを聞いたりするのに困る。いったい何が宿題なのかよくわからないことが多々あるからだ。だから、どんなクラスでも親しい友だちは必ずひとりは作っておくようにした。
だいたい普通の授業は1教科3クレジット(単位)で、週に2、3回ある。週に2回しかない授業は1回の授業がだいたい3時間で、3回ある場合は2時間の授業になっていた。私は、アメリカに来て一年目は、ELSの授業のほかには、アナ先生などイングリッシュだけの一般授業をひとつ、ノン・ディグリーとしてとった。
ELSは、“英語は第二外国語”というクラスなので、先生も英語が分かるように説明してくれるが、大学の一般の授業ではネイティブな人に教えるわけだから、私のような外国人のために講義のスピード速度はけっして緩めない。それでも、講義の内容は決まっているし、テキストもあるから、なんとか理解しようと思えば、英語自体はわからなくても推測がつくところがあったが、他の学生たちの発言にいたっては聞き取るのが至難だった。みんな話し方は様々だし、彼らがプレゼンテーションをしたり、意見を述べる時は、本当に聞き取りにくくて、頭をかきむしりたくなることもしばしばだった。
こうした短期講座のひとつ、最初の夏の“サマーセッション”で、私は念願のアナ・チャーターズ先生の授業をとることにした。私が日本から手紙を書いた、あの英文学の女性教授である。その先生は、当時アメリカの現代作家でレイモンド・カーヴァ-という作家の作品についての講義をしていた。カーヴァーは、日本では村上春樹さんによって翻訳されていることでも有名だが、その先生の授業で短編を読んで感想文を提出した。
私が書いたのは、いわば英作文の延長のようなもので、つぎのようなことだったと思う。“カーヴァーは努力して作家になった。努力は貴重なものであり、継続も力である。自分がやりたいことを最後まで貫き通すことが、幸せになる秘訣なのだ。”
これを読んだ先生が、たまたま次の年に使う教科書を作成しているところで、私の感想文を読んで面白いので、教科書のなかで使いたい、と私に言ってきた。びくり仰天して、「どうして?」と聞くと、「初歩的な英語の書き方として参考になるから」と、先生はいう。私はもちろん、名誉なことなのでOKして、同時になんだかわけがわからないうちに、書類にサインさせられた。それは、原稿料として私にも100ドルくれるという内容のものだった。すると、しばらくしてちゃんと100ドルの原稿料が届いた。とにかくラッキーだった。大げさに言えば、アメリカという国は、次から次に信じられないことが起こるもんだ。
でも、それと同時に感じたのは、アメリカの契約や著作権に対する考え方のきちっとしているところである。日本なら断りもなく、勝手に引用してしまうかもしれないが、アメリカではきちんと許可を得る。アメリカの著作権は、日本とは比べものにならない。これもアメリカのひとつの顔かもしれない。
また、私はELSの授業のほかに、春や夏に短期で行われる講座の授業も少しとっていた。ここでは、宿題はでないが、これも予習していかないと授業にはついていけず、勉強時間の配分がむずかしかった。
一般の講座はアメリカ人を対象にしているので、もちろん若い学生ばかり。自分の息子と娘と同じ世代ばかりである。そのなかで私のような中年の、まして外国人の女性となるとひとりだけ。当たり前だろう。「あ、おばさんが日本から来ているんだな。どういう理由で来ているのかな」といった感想をもっていたとは思う。でも、決して好奇の目でみるようなことはなかった。よっぽど親しくなった学生が、いろいろ聞いてくるので、私は正直に答えた。
「歳はいくつ?」
「女の人に歳を聞くもんじゃないわよ」
「お母さんくらいかな」
「そう、あなたのお母さんくらいかな」
「ふーん、どうして大学にきているの」
「昔からの夢で、アメリカの大学卒業したかったから」
「えらいねー、うちのお母さんにも言ってやろう」
なんていう話になる。でも、それ以上にあれこれ聞いてくることはない。歳も離れているから、学校外でのつきあいというのはほとんどない。とはいっても、少しは親しい友だちをつくっておかないと、授業のことを聞いたりするのに困る。いったい何が宿題なのかよくわからないことが多々あるからだ。だから、どんなクラスでも親しい友だちは必ずひとりは作っておくようにした。
だいたい普通の授業は1教科3クレジット(単位)で、週に2、3回ある。週に2回しかない授業は1回の授業がだいたい3時間で、3回ある場合は2時間の授業になっていた。私は、アメリカに来て一年目は、ELSの授業のほかには、アナ先生などイングリッシュだけの一般授業をひとつ、ノン・ディグリーとしてとった。
ELSは、“英語は第二外国語”というクラスなので、先生も英語が分かるように説明してくれるが、大学の一般の授業ではネイティブな人に教えるわけだから、私のような外国人のために講義のスピード速度はけっして緩めない。それでも、講義の内容は決まっているし、テキストもあるから、なんとか理解しようと思えば、英語自体はわからなくても推測がつくところがあったが、他の学生たちの発言にいたっては聞き取るのが至難だった。みんな話し方は様々だし、彼らがプレゼンテーションをしたり、意見を述べる時は、本当に聞き取りにくくて、頭をかきむしりたくなることもしばしばだった。
こうした短期講座のひとつ、最初の夏の“サマーセッション”で、私は念願のアナ・チャーターズ先生の授業をとることにした。私が日本から手紙を書いた、あの英文学の女性教授である。その先生は、当時アメリカの現代作家でレイモンド・カーヴァ-という作家の作品についての講義をしていた。カーヴァーは、日本では村上春樹さんによって翻訳されていることでも有名だが、その先生の授業で短編を読んで感想文を提出した。
私が書いたのは、いわば英作文の延長のようなもので、つぎのようなことだったと思う。“カーヴァーは努力して作家になった。努力は貴重なものであり、継続も力である。自分がやりたいことを最後まで貫き通すことが、幸せになる秘訣なのだ。”
これを読んだ先生が、たまたま次の年に使う教科書を作成しているところで、私の感想文を読んで面白いので、教科書のなかで使いたい、と私に言ってきた。びくり仰天して、「どうして?」と聞くと、「初歩的な英語の書き方として参考になるから」と、先生はいう。私はもちろん、名誉なことなのでOKして、同時になんだかわけがわからないうちに、書類にサインさせられた。それは、原稿料として私にも100ドルくれるという内容のものだった。すると、しばらくしてちゃんと100ドルの原稿料が届いた。とにかくラッキーだった。大げさに言えば、アメリカという国は、次から次に信じられないことが起こるもんだ。
でも、それと同時に感じたのは、アメリカの契約や著作権に対する考え方のきちっとしているところである。日本なら断りもなく、勝手に引用してしまうかもしれないが、アメリカではきちんと許可を得る。アメリカの著作権は、日本とは比べものにならない。これもアメリカのひとつの顔かもしれない。