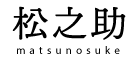エッセイ
ESSAY
ESSAY


Ⅰ 主婦が見た夢
1.アメリカ留学の夢
2.イリノイへの招待
3.幻の留学
4.私への投資は800万円
5.英語との格闘はじまる
6.多国籍クラスのなかで
7.地下のキッチンでの日本食
8.作文が教科書に掲載される
9.若いころもっと本を読んでいれば
10.中国人留学生の死
11.アメリカ式ストレス解消法
12.ようやく正規の大学生として
13.自立するアメリカの学生
14.ドライブ・デビュー
15.驚異のシルバーパワー
16.ニューヨークへひとっ飛び
17.大陸横断旅行
Ⅱ アメリカンケーキへの道
18.アメリカン・ケーキとの出会い
19.おしかけて、弟子入り
20.グレート・アメリカンケーキへの道
21.グレート・アメリカン・アップル・パイの
作り方のポイント
22.セカンド・イズ・ザ・ベスト
23.ベースボールとアメリカン・ケーキ
24.歴史で味わうケーキ作り
25.未知のケーキとの遭遇(1)
26.未知のケーキとの遭遇(2)
27.卒業
28.遅すぎることはない
29.あとがき
16
ニューヨークへひとっ飛び
平日はまったく時間的なゆとりのない生活を送っていたし、休日でも、追いつかない分の予習復習をすることもしばしばだった。しかし、だからだといって、まったくオフがなかったわけではもちろんない。気分を変えて、休日に車で一人、時間をみつけてはニューヨークまででかけていった。
ニューヨークまで行く学生でも、車で出かけるのは怖いので、あまり行く人はいなかったが、私は運転技術にも自信がついたし、行動の自由もきくのでドライブに挑戦した。
映画や舞台が好きだったこともあるし、田舎ではみられない様々な人々や文化に出逢える楽しみがあった。あんまり田舎にいると、田舎のおばさんになってしまう。もちろん、田舎は純朴で素晴らしいところがあるのだが、たまに、ニューヨークで背筋のピンと伸びた女性たちを見ると、いい刺激になった。
ニューヨークまでのドライブは車で2時間半から3時間。ルートは3,4種類あるのだが、私の通る道は決まっていた。高速道路の91号線を南下して、途中で15号線に乗り換える。この15号線は、道幅が狭くて蛇行していて運転は難しい。しかし、トラックなどコマーシャル・ビークルが通行禁止になっているので、視界が広がっていて、私はこの道が大好きだった。
特に、夏休みに同級生の青年と大陸横断のドライブを達成したあとは運転の技術も上がり、頻繁にこの道路を走った。ニューヨークは怖いまちなのはわかってはいた。イエローキャブの運転は荒っぽいし、できるだけ慎重に心がけた。マンハッタンの駐車場はとても高かったが、土日は路上駐車OKだったので、車を止めてまちなかに出ていった。
ニューヨークへは、今回アメリカに来る前は一度も行ったことはなかった。そもそも20年以上前、初めてイリノイを訪れて以来、外国に旅行することなどなかった。それどころか、結婚して以来、一度も旅行などというものに行ったことがなかった。夫は旅行がきらいだったし、ひとりで行くことなんて許されなかった。ある時、旅行に行きたいといったら「ぼくが働いているのに、なんであなたひとりで旅行に行かなくてはいけないの」と言われたことがある。
もともと個人的には旅行は好きだし、いろんな所へ行ってみたいという気持ちはどこかにあった。ニューヨークへも、いつか行ってみたいなという漠然とした憧れはあった。でも、それが実現できる可能性がまったくないのなら、そんなことを思ったらかえってしんどいから、やめておこう、そう思うようにしていた。
いま考えれば、私と夫とは、考え方も、生き方も、ひょっとすると家のなかで見ていたものも違っていたような気がする。間に子どもがいて、それぞれが子どもの手を反対側でつないで、それでつながっていたような気がする。
私が、海外旅行に行っていたような主婦だったら、この歳になって留学してアメリカに来ようなんて思わなかったかも知れない。だから、今回のアメリカ行きも、「20年以上眠っていたものが爆発したのかもしれない」なんて思うときもある。でも、実際はよくわからない。なぜなら、アメリカで勉強したこともなんだか、夢のような出来事で、どう考えたらいいのかわからないからだ。
主婦をしていたころの友達は、他府県から来ていただけに柔軟な人たちだった。人のうわさ話で面白がるようなことはしないようにしようと、話していた人たちだった。が、それでも私が「留学する」と言ったときは「え!」と絶句していた。
ニューヨークに行くときもいつも1人だった。それは、急に空いた時間を利用するからで、とてもほかの人を誘うという余裕はなかった。仮に誘うといっても、自分の娘か息子の歳だし、クラスでも「お母さん」になってしまうので、同い年といえば大学の先生くらい。素敵な先生もいたが、残念ながらそうした人と親しくする余裕もなかったのだ。もし、これが若いときだったら。ま、そんなことを言っても始まらない。
ニューヨークは見るものも新鮮で飽きることがないから、私はひとりでもまったく寂しくはなかった。が、トラブルに巻き込まれたときは、さすがにどうしようかと心細かった。それは、一度だけだったのだが、置き引きにあったののである。
その日のニューヨーク行きも、いつものようにハドソン川沿いの9Aという道を快調に走り、よく行くバーニーズの地下のレストランで昼食をとった。ここは坂本龍一のお気に入りのレストランでもあると知って訪れて以来、私もすっかり気に入ってしまった。
昼食後、カツラを買いたくなり、マンハッタンの南、5thアベニューの15ストリートに足を踏み入れた。道路沿いに駐車をして目的の店に入った。この付近は、日本で言うなら100円ショップのような安売り店が軒を連ねていて、あまり安全な場所ではないが、日中はそれほど危険なことはない。
二軒ならぶカツラ屋の一軒目で3個のカツラを買い、次の店に入った。店内には2人の店員がいて、客は私と黒人の女性と2人の子ども、そして、白人女性の三人組だった。私は前の店で買ったカツラの入った紙袋をカウンターの上に置き、そしてカツラの試着をはじめた。そして、ふと気がつくと袋がない!その間わずか1、2分である。
店内には、外国人の旅行者が3人と、オカマの男性1人が入ってきていて混雑してきた。周りを見ると、さっきまでいた子ども連れの女性がいない。「しまった。置き引きだ」 と、思ったときは遅かった。カツラは120ドル。決して安くはない。私の不注意だ。
警察に行ってもカツラは戻らないだろうし、お店にも迷惑がかかると思った私はあきらめて外へ出た。「無事だっただけよかったじゃないの」と、自分に言い聞かせてみた。すると、先ほどの子づれの女性が別の店から出てきたではないか。子どもが私のカツラが入ったと思われる袋を下げている。
「ちょっと、聞いてみよう」 「だがまてよ、もし犯人扱いをして間違いだったら、名誉毀損で訴えられるかもしれない」 じわじわと汗ばむ背中を感じながら、頭の中では冷静に、彼女にかけるべき言葉を探していた。そして、言ってみた。 「さっきカツラの入った袋をなくしたんですが、この子が持っている袋とそっくりなので…」 すると、女性は、 「これ、その店で買ったのよ」という。 「そうですか、でも私はそれと同じ物を買ったので、もう一度その店に一緒にいってくれますか。同じものを買いたいので」 すると、彼女はあっさりとその袋を私に渡してくれた。そして、子どもと一緒にゆっくりとあるきはじめた。」私は、急に足がガクガクと震えてきた。カツラ店に引き返し、カツラが出てきたことを説明して、足早に車に戻りニューヨークをあとにした。
それまで、アメリカで怖い思いをしてこなかったが、それはラッキーだったのかもしれない。ハドソン川の風を感じながら、「それにしても、あの2人の子どもたちは、この先いったいどうなるのだろう」と、思ってしまった。
ニューヨークまで行く学生でも、車で出かけるのは怖いので、あまり行く人はいなかったが、私は運転技術にも自信がついたし、行動の自由もきくのでドライブに挑戦した。
映画や舞台が好きだったこともあるし、田舎ではみられない様々な人々や文化に出逢える楽しみがあった。あんまり田舎にいると、田舎のおばさんになってしまう。もちろん、田舎は純朴で素晴らしいところがあるのだが、たまに、ニューヨークで背筋のピンと伸びた女性たちを見ると、いい刺激になった。
ニューヨークまでのドライブは車で2時間半から3時間。ルートは3,4種類あるのだが、私の通る道は決まっていた。高速道路の91号線を南下して、途中で15号線に乗り換える。この15号線は、道幅が狭くて蛇行していて運転は難しい。しかし、トラックなどコマーシャル・ビークルが通行禁止になっているので、視界が広がっていて、私はこの道が大好きだった。
特に、夏休みに同級生の青年と大陸横断のドライブを達成したあとは運転の技術も上がり、頻繁にこの道路を走った。ニューヨークは怖いまちなのはわかってはいた。イエローキャブの運転は荒っぽいし、できるだけ慎重に心がけた。マンハッタンの駐車場はとても高かったが、土日は路上駐車OKだったので、車を止めてまちなかに出ていった。
ニューヨークへは、今回アメリカに来る前は一度も行ったことはなかった。そもそも20年以上前、初めてイリノイを訪れて以来、外国に旅行することなどなかった。それどころか、結婚して以来、一度も旅行などというものに行ったことがなかった。夫は旅行がきらいだったし、ひとりで行くことなんて許されなかった。ある時、旅行に行きたいといったら「ぼくが働いているのに、なんであなたひとりで旅行に行かなくてはいけないの」と言われたことがある。
もともと個人的には旅行は好きだし、いろんな所へ行ってみたいという気持ちはどこかにあった。ニューヨークへも、いつか行ってみたいなという漠然とした憧れはあった。でも、それが実現できる可能性がまったくないのなら、そんなことを思ったらかえってしんどいから、やめておこう、そう思うようにしていた。
いま考えれば、私と夫とは、考え方も、生き方も、ひょっとすると家のなかで見ていたものも違っていたような気がする。間に子どもがいて、それぞれが子どもの手を反対側でつないで、それでつながっていたような気がする。
私が、海外旅行に行っていたような主婦だったら、この歳になって留学してアメリカに来ようなんて思わなかったかも知れない。だから、今回のアメリカ行きも、「20年以上眠っていたものが爆発したのかもしれない」なんて思うときもある。でも、実際はよくわからない。なぜなら、アメリカで勉強したこともなんだか、夢のような出来事で、どう考えたらいいのかわからないからだ。
主婦をしていたころの友達は、他府県から来ていただけに柔軟な人たちだった。人のうわさ話で面白がるようなことはしないようにしようと、話していた人たちだった。が、それでも私が「留学する」と言ったときは「え!」と絶句していた。
ニューヨークに行くときもいつも1人だった。それは、急に空いた時間を利用するからで、とてもほかの人を誘うという余裕はなかった。仮に誘うといっても、自分の娘か息子の歳だし、クラスでも「お母さん」になってしまうので、同い年といえば大学の先生くらい。素敵な先生もいたが、残念ながらそうした人と親しくする余裕もなかったのだ。もし、これが若いときだったら。ま、そんなことを言っても始まらない。
ニューヨークは見るものも新鮮で飽きることがないから、私はひとりでもまったく寂しくはなかった。が、トラブルに巻き込まれたときは、さすがにどうしようかと心細かった。それは、一度だけだったのだが、置き引きにあったののである。
その日のニューヨーク行きも、いつものようにハドソン川沿いの9Aという道を快調に走り、よく行くバーニーズの地下のレストランで昼食をとった。ここは坂本龍一のお気に入りのレストランでもあると知って訪れて以来、私もすっかり気に入ってしまった。
昼食後、カツラを買いたくなり、マンハッタンの南、5thアベニューの15ストリートに足を踏み入れた。道路沿いに駐車をして目的の店に入った。この付近は、日本で言うなら100円ショップのような安売り店が軒を連ねていて、あまり安全な場所ではないが、日中はそれほど危険なことはない。
二軒ならぶカツラ屋の一軒目で3個のカツラを買い、次の店に入った。店内には2人の店員がいて、客は私と黒人の女性と2人の子ども、そして、白人女性の三人組だった。私は前の店で買ったカツラの入った紙袋をカウンターの上に置き、そしてカツラの試着をはじめた。そして、ふと気がつくと袋がない!その間わずか1、2分である。
店内には、外国人の旅行者が3人と、オカマの男性1人が入ってきていて混雑してきた。周りを見ると、さっきまでいた子ども連れの女性がいない。「しまった。置き引きだ」 と、思ったときは遅かった。カツラは120ドル。決して安くはない。私の不注意だ。
警察に行ってもカツラは戻らないだろうし、お店にも迷惑がかかると思った私はあきらめて外へ出た。「無事だっただけよかったじゃないの」と、自分に言い聞かせてみた。すると、先ほどの子づれの女性が別の店から出てきたではないか。子どもが私のカツラが入ったと思われる袋を下げている。
「ちょっと、聞いてみよう」 「だがまてよ、もし犯人扱いをして間違いだったら、名誉毀損で訴えられるかもしれない」 じわじわと汗ばむ背中を感じながら、頭の中では冷静に、彼女にかけるべき言葉を探していた。そして、言ってみた。 「さっきカツラの入った袋をなくしたんですが、この子が持っている袋とそっくりなので…」 すると、女性は、 「これ、その店で買ったのよ」という。 「そうですか、でも私はそれと同じ物を買ったので、もう一度その店に一緒にいってくれますか。同じものを買いたいので」 すると、彼女はあっさりとその袋を私に渡してくれた。そして、子どもと一緒にゆっくりとあるきはじめた。」私は、急に足がガクガクと震えてきた。カツラ店に引き返し、カツラが出てきたことを説明して、足早に車に戻りニューヨークをあとにした。
それまで、アメリカで怖い思いをしてこなかったが、それはラッキーだったのかもしれない。ハドソン川の風を感じながら、「それにしても、あの2人の子どもたちは、この先いったいどうなるのだろう」と、思ってしまった。