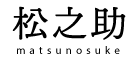エッセイ
ESSAY
ESSAY


Ⅰ 主婦が見た夢
1.アメリカ留学の夢
2.イリノイへの招待
3.幻の留学
4.私への投資は800万円
5.英語との格闘はじまる
6.多国籍クラスのなかで
7.地下のキッチンでの日本食
8.作文が教科書に掲載される
9.若いころもっと本を読んでいれば
10.中国人留学生の死
11.アメリカ式ストレス解消法
12.ようやく正規の大学生として
13.自立するアメリカの学生
14.ドライブ・デビュー
15.驚異のシルバーパワー
16.ニューヨークへひとっ飛び
17.大陸横断旅行
Ⅱ アメリカンケーキへの道
18.アメリカン・ケーキとの出会い
19.おしかけて、弟子入り
20.グレート・アメリカンケーキへの道
21.グレート・アメリカン・アップル・パイの
作り方のポイント
22.セカンド・イズ・ザ・ベスト
23.ベースボールとアメリカン・ケーキ
24.歴史で味わうケーキ作り
25.未知のケーキとの遭遇(1)
26.未知のケーキとの遭遇(2)
27.卒業
28.遅すぎることはない
29.あとがき
24
歴史で味わうケーキ作り
ローリー先生の次にケーキを習いに行ったのが、プリューデンス・サローンというこれも女性で、この先生は、教えることを本業としている人だった。地方の名士でもあり、家でベーキング・スクールを開いているほか、コネチカットのラジオ番組でフードコンサルタントをしてる。雑誌にも登場している有名人だった。その意味では前の先生とはまったく違うタイプの人だった。
この人は人当たりはよく、教えるのも上手だった。ただ、彼女のスクールは包丁の研ぎ方をはじめクッキング全般を教えるので、私はそのなかでベーキングがある時だけ、だいたい1ヶ月に1度くらい通っていた。しかも、それはヨーロッパのベーキングが中心だったので、一通り彼女の指導を受けてから、「ニューイングランドに伝わるベーキングを教えてくれる先生を紹介してほしい」と、この先生に相談した。
そして紹介してもらったのが、三人目の先生となる、シャロル・ジーン先生だった。この先生に出会ったことが私にとって最高の幸せだったといえる。彼女が、私にきちんとニューイングランドのベーキングを教えてくれた。
それぞれの先生から、時期的に重複して教えてもらっている時もあり、比較しながらアメリカのクッキング、ベーキングを知ることもできたが、なかでもシャロル先生との出会いが私にケーキ作りの深みを教えてくれた。
彼女は、もともとインテリアデザイナーだったが、これを18年間経験したあと、CIAという(中央情報機関ではない)、全米で最も権威ある料理学校を卒業し、その後4つ星のレストランで修行をして、自分でも料理学校を経営している料理人であり、指導者だった。彼女は、クリントン大統領のヒラリー夫人が主催するクリスマス会に招待されるくらいの人物である。彼女が最終的には私の師匠になり、彼女の学校の終了証書を私はもらうことができた。
その学校に、週に平均すると2、3回、高速道路を車で片道1時間かけて、帰国する前年の9月から翌年の5月まで通うことになった。彼女のところは、時間的にも自由がきいて、私のためだけのプライベート・レッスンも受けることができた。時間は朝の10時から午後1時までくらいが普通だったが、時には朝10時から夕方の5時頃までずっと指導を受けることもあった。
この先生のスクールは、買い取った教会を改装して教えていたのだが、たまたま私が習うころには改装の最中だったので、私は彼女の自宅のキッチンで手とり足とり教えてもらうことができた。しかし、それでも大学の授業があるので、月に1度くらいはプリューデンス先生のところにも通っていた。
シャロル先生は、単にケーキ作りだけではなく、ニューイングランドの歴史との関係から料理の話をしてくれたりした。読むべき本も勧めてくれた。一つのケーキにもさまざまなストーリーが背後に潜んでいることがあるのだ。
ちょっと、アメリカの歴史をケーキとの関係でひもといてみたい。アメリカの歴史は、ニューイングランドから始まる。ニューイングランドとは、アメリカ北東部の6つの小さな州(コネチカット、メイン、マサチューセッツ、ニューハンプシャー、ロードアイランド、バーモント)からなる。代表的な都市はボストンで、歴史の教科書にも出てくるボストン茶会事件が有名だ。まだ、イギリスの植民地だった1773年、本国イギリスの不当な茶税に怒ったアメリカ入植者が、ボストン港に茶箱を投げ込み、独立戦争の発端となった事件だ。
このころ、アメリカは豊かではなかった。地図で見ていただけばわかるが、ニューイングランドはアメリカの北のはずれ、緯度でいえば青森から札幌と同じで当然寒い。10月から4月まで、雪と氷に閉ざされる。土地はやせていて、森林が多く農業にもむかない。入植者は貧しく、18世紀の初めだから技術もなく、入植最初の冬は、人口の半分以上が死滅したという。
その清教徒を救ったのがアメリカインディアンである。彼らは、トウモロコシ、パンプキン(日本のカボチャとはちょっと違う)、クランベリーなどのニューイングランド土着の食べ物の使い方を、清教徒たちに伝授した。ここに、ヨーロッパ的ではない、アメリカの料理のオリジナリティーが端を発するのだ。
例えば、トウモロコシを挽いた粉であるコーンミールと砂糖を混ぜて焼いた「インディアン・プディング」。現在でも感謝祭(Thanksgiving day)に欠かせないパンプキンパイ。どちらも素朴な味わいだ。繊細さではヨーロッパには劣るが、厳しい自然との戦いのなかで生み出された味わいがある。
ニューイングランドから、アメリカ人は広大な大地を開拓した。もちろん、農民として彼らの生活は自然のなかではじまった。一日の始まりに、アップルパイを平らげる。リンゴの木なら自生している。黄金色に焼けた甘酸っぱい香りのパイを大きく切り分けて、厳しい労働のエネルギーにする。
開拓時代のアメリカでは、まずおいしいアップルパイを焼けることがよき花嫁の条件だったと聞く。ちょうど日本でうまい漬物をつけられるのが、好ましい嫁の条件だったように。漬物のように家庭の数だけ異なるアップルパイの味があったという。牛乳からバターをとったあとのバターミルクも、マフィンやクッキー、ドーナツにフルに利用され、肉体労働に消耗した人々の間食となった。
甘いもの、それは彼らにとっては、単に食事のあとのお楽しみにとどまるものではなかった。それは、アメリカのフロンティア・スピリットを支える、なくてはならないエネルギーの源だったのである。だから、アメリカの伝統的な甘さは歴史、文化、生活そのものなのだ。“As American as apple pie” という言葉がある。直訳すれば、「アップルパイみたいにアメリカンな」となるが、これは「とてもアメリカ的な」という意味だ。味噌汁が日本のお袋の味ならアップルパイはそのアメリカ版だ。パイやケーキ(アメリカではブレッドと呼ばれる)、ドーナツやマフィン、その他ありとあらゆる甘いものが、アメリカ人の生活の中に根ざしている。
ヘルスコンシャスな今日だが、それでも多くの人が朝からもりもりと甘いマフィンを平らげて仕事に出かける。おやつはアメリカンコーヒーとドーナツ。1ダース3ドルくらいで売っている。食後はなにはともあれ、デザート。人が集まれば、パイやケーキが会話に華を添える。
私もむくつけき大男から、お礼にとお手製のケーキをもらったことがある。料理をよく知っているとは言えないアメリカ人でも、なぜかお菓子の一つ、二つは作り方を心得ているらしい。甘いものが苦手だというアメリカ人を私はまだ知らない。
歴史や文化を合わせてケーキ作りを学ぶことで、ケーキに対する興味がさらにわいてくる。例えば、インディアン・プディングは、イギリス人がメイフラワー号に乗って初めてアメリカにやってきたときに生まれたもので、インディアンに助けられて、翌年から豊作に恵まれたのを祝って作ったものだということを知り、その味に対する想像力がふくらむのである。
この人は人当たりはよく、教えるのも上手だった。ただ、彼女のスクールは包丁の研ぎ方をはじめクッキング全般を教えるので、私はそのなかでベーキングがある時だけ、だいたい1ヶ月に1度くらい通っていた。しかも、それはヨーロッパのベーキングが中心だったので、一通り彼女の指導を受けてから、「ニューイングランドに伝わるベーキングを教えてくれる先生を紹介してほしい」と、この先生に相談した。
そして紹介してもらったのが、三人目の先生となる、シャロル・ジーン先生だった。この先生に出会ったことが私にとって最高の幸せだったといえる。彼女が、私にきちんとニューイングランドのベーキングを教えてくれた。
それぞれの先生から、時期的に重複して教えてもらっている時もあり、比較しながらアメリカのクッキング、ベーキングを知ることもできたが、なかでもシャロル先生との出会いが私にケーキ作りの深みを教えてくれた。
彼女は、もともとインテリアデザイナーだったが、これを18年間経験したあと、CIAという(中央情報機関ではない)、全米で最も権威ある料理学校を卒業し、その後4つ星のレストランで修行をして、自分でも料理学校を経営している料理人であり、指導者だった。彼女は、クリントン大統領のヒラリー夫人が主催するクリスマス会に招待されるくらいの人物である。彼女が最終的には私の師匠になり、彼女の学校の終了証書を私はもらうことができた。
その学校に、週に平均すると2、3回、高速道路を車で片道1時間かけて、帰国する前年の9月から翌年の5月まで通うことになった。彼女のところは、時間的にも自由がきいて、私のためだけのプライベート・レッスンも受けることができた。時間は朝の10時から午後1時までくらいが普通だったが、時には朝10時から夕方の5時頃までずっと指導を受けることもあった。
この先生のスクールは、買い取った教会を改装して教えていたのだが、たまたま私が習うころには改装の最中だったので、私は彼女の自宅のキッチンで手とり足とり教えてもらうことができた。しかし、それでも大学の授業があるので、月に1度くらいはプリューデンス先生のところにも通っていた。
シャロル先生は、単にケーキ作りだけではなく、ニューイングランドの歴史との関係から料理の話をしてくれたりした。読むべき本も勧めてくれた。一つのケーキにもさまざまなストーリーが背後に潜んでいることがあるのだ。
ちょっと、アメリカの歴史をケーキとの関係でひもといてみたい。アメリカの歴史は、ニューイングランドから始まる。ニューイングランドとは、アメリカ北東部の6つの小さな州(コネチカット、メイン、マサチューセッツ、ニューハンプシャー、ロードアイランド、バーモント)からなる。代表的な都市はボストンで、歴史の教科書にも出てくるボストン茶会事件が有名だ。まだ、イギリスの植民地だった1773年、本国イギリスの不当な茶税に怒ったアメリカ入植者が、ボストン港に茶箱を投げ込み、独立戦争の発端となった事件だ。
このころ、アメリカは豊かではなかった。地図で見ていただけばわかるが、ニューイングランドはアメリカの北のはずれ、緯度でいえば青森から札幌と同じで当然寒い。10月から4月まで、雪と氷に閉ざされる。土地はやせていて、森林が多く農業にもむかない。入植者は貧しく、18世紀の初めだから技術もなく、入植最初の冬は、人口の半分以上が死滅したという。
その清教徒を救ったのがアメリカインディアンである。彼らは、トウモロコシ、パンプキン(日本のカボチャとはちょっと違う)、クランベリーなどのニューイングランド土着の食べ物の使い方を、清教徒たちに伝授した。ここに、ヨーロッパ的ではない、アメリカの料理のオリジナリティーが端を発するのだ。
例えば、トウモロコシを挽いた粉であるコーンミールと砂糖を混ぜて焼いた「インディアン・プディング」。現在でも感謝祭(Thanksgiving day)に欠かせないパンプキンパイ。どちらも素朴な味わいだ。繊細さではヨーロッパには劣るが、厳しい自然との戦いのなかで生み出された味わいがある。
ニューイングランドから、アメリカ人は広大な大地を開拓した。もちろん、農民として彼らの生活は自然のなかではじまった。一日の始まりに、アップルパイを平らげる。リンゴの木なら自生している。黄金色に焼けた甘酸っぱい香りのパイを大きく切り分けて、厳しい労働のエネルギーにする。
開拓時代のアメリカでは、まずおいしいアップルパイを焼けることがよき花嫁の条件だったと聞く。ちょうど日本でうまい漬物をつけられるのが、好ましい嫁の条件だったように。漬物のように家庭の数だけ異なるアップルパイの味があったという。牛乳からバターをとったあとのバターミルクも、マフィンやクッキー、ドーナツにフルに利用され、肉体労働に消耗した人々の間食となった。
甘いもの、それは彼らにとっては、単に食事のあとのお楽しみにとどまるものではなかった。それは、アメリカのフロンティア・スピリットを支える、なくてはならないエネルギーの源だったのである。だから、アメリカの伝統的な甘さは歴史、文化、生活そのものなのだ。“As American as apple pie” という言葉がある。直訳すれば、「アップルパイみたいにアメリカンな」となるが、これは「とてもアメリカ的な」という意味だ。味噌汁が日本のお袋の味ならアップルパイはそのアメリカ版だ。パイやケーキ(アメリカではブレッドと呼ばれる)、ドーナツやマフィン、その他ありとあらゆる甘いものが、アメリカ人の生活の中に根ざしている。
ヘルスコンシャスな今日だが、それでも多くの人が朝からもりもりと甘いマフィンを平らげて仕事に出かける。おやつはアメリカンコーヒーとドーナツ。1ダース3ドルくらいで売っている。食後はなにはともあれ、デザート。人が集まれば、パイやケーキが会話に華を添える。
私もむくつけき大男から、お礼にとお手製のケーキをもらったことがある。料理をよく知っているとは言えないアメリカ人でも、なぜかお菓子の一つ、二つは作り方を心得ているらしい。甘いものが苦手だというアメリカ人を私はまだ知らない。
歴史や文化を合わせてケーキ作りを学ぶことで、ケーキに対する興味がさらにわいてくる。例えば、インディアン・プディングは、イギリス人がメイフラワー号に乗って初めてアメリカにやってきたときに生まれたもので、インディアンに助けられて、翌年から豊作に恵まれたのを祝って作ったものだということを知り、その味に対する想像力がふくらむのである。