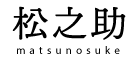エッセイ
ESSAY
ESSAY


Ⅰ 主婦が見た夢
1.アメリカ留学の夢
2.イリノイへの招待
3.幻の留学
4.私への投資は800万円
5.英語との格闘はじまる
6.多国籍クラスのなかで
7.地下のキッチンでの日本食
8.作文が教科書に掲載される
9.若いころもっと本を読んでいれば
10.中国人留学生の死
11.アメリカ式ストレス解消法
12.ようやく正規の大学生として
13.自立するアメリカの学生
14.ドライブ・デビュー
15.驚異のシルバーパワー
16.ニューヨークへひとっ飛び
17.大陸横断旅行
Ⅱ アメリカンケーキへの道
18.アメリカン・ケーキとの出会い
19.おしかけて、弟子入り
20.グレート・アメリカンケーキへの道
21.グレート・アメリカン・アップル・パイの
作り方のポイント
22.セカンド・イズ・ザ・ベスト
23.ベースボールとアメリカン・ケーキ
24.歴史で味わうケーキ作り
25.未知のケーキとの遭遇(1)
26.未知のケーキとの遭遇(2)
27.卒業
28.遅すぎることはない
29.あとがき
19
おしかけて、弟子入り
どこで、習ったらいいものか。いろいろ考えながらキャンパスを歩いていると、「犬も歩けば棒にあたる」ではないが、おいしいケーキに出合ったのである。
キャンパスの中では、毎月第二土曜日だったか、日本で言えば、野菜など食品を売るマーケットが開かれていた。大学生や大学の職員たちがこれをよく利用していた。そのなかの一つにリトルリバー・ベーカリーというお手製のケーキを売る小さな店があった。それをたまたま食べてみると、ものすごくおいしい。
「よし、この人に教えてもらえるかどうか聞いてみよう」思い立ったが吉日。さっそく電話番号を調べて連絡してみた。すると、アメリカ式のビジネスライクな返答が返ってきた。それは、アメリカのおいしいケーキを作って売っている女性の声だった。私と同じくらいの年齢だろうか。「あなたに捧げる時間は、私にはありませんわ。私はベーカリーを経営していてとてもそんな時間はないの」と、はっきり断られた。しかし、それであきらめはしなかった。
「これで引き下がったら、もう何もできやしない」単なる趣味じゃない、日本に帰ってからの自分の生活がかかっているんだ、という必死の思いがあったからかもしれない。もう一度挑戦してみた。「あなたが作ったケーキはほんとうにおいしかった。私はいま日本から大学に来て勉強しているが、年齢もいっているし、日本に帰ったら将来ベーキングの世界で食べていきたい」と、電話で話した。でも、断られた。それならと、今度は私は彼女の家を探し出して押しかけていった。今日女の意地である。
「どうしてもお願いします」と、必死にたのんだ。すると、彼女は、「私の空いている時間でいいのなら、1週間に一度、2時間だけ、あなたのために時間をあけましょう。ただし、それも大学のオープンマーケットをやらない秋から冬にかけての期間なら、という条件です」と、言ってくれた。冬は雪が深く、寒いので戸外でのマーケットはやらないから、その期間は彼女は比較的時間があるのだという。
彼女の名前は、ローリー・プライブルといって、私と同年齢くらいで、手づくりのパンやケーキをレストランに卸したり、同時に個人のお客さんの電話での注文に応じてパンやケーキを作っている。まさに地域に根差したベーカリーだった。住まいのすぐそばに工房をもって、彼女は毎日そこで黙々と働く“職人”だった。
やがて、冬が近づきキャンパス内のマーケットはなくなり、ELSに通っていた私は毎水曜日になると、ケーキを習いにプライブル先生の店に通っていった。
キャンパスの中では、毎月第二土曜日だったか、日本で言えば、野菜など食品を売るマーケットが開かれていた。大学生や大学の職員たちがこれをよく利用していた。そのなかの一つにリトルリバー・ベーカリーというお手製のケーキを売る小さな店があった。それをたまたま食べてみると、ものすごくおいしい。
「よし、この人に教えてもらえるかどうか聞いてみよう」思い立ったが吉日。さっそく電話番号を調べて連絡してみた。すると、アメリカ式のビジネスライクな返答が返ってきた。それは、アメリカのおいしいケーキを作って売っている女性の声だった。私と同じくらいの年齢だろうか。「あなたに捧げる時間は、私にはありませんわ。私はベーカリーを経営していてとてもそんな時間はないの」と、はっきり断られた。しかし、それであきらめはしなかった。
「これで引き下がったら、もう何もできやしない」単なる趣味じゃない、日本に帰ってからの自分の生活がかかっているんだ、という必死の思いがあったからかもしれない。もう一度挑戦してみた。「あなたが作ったケーキはほんとうにおいしかった。私はいま日本から大学に来て勉強しているが、年齢もいっているし、日本に帰ったら将来ベーキングの世界で食べていきたい」と、電話で話した。でも、断られた。それならと、今度は私は彼女の家を探し出して押しかけていった。今日女の意地である。
「どうしてもお願いします」と、必死にたのんだ。すると、彼女は、「私の空いている時間でいいのなら、1週間に一度、2時間だけ、あなたのために時間をあけましょう。ただし、それも大学のオープンマーケットをやらない秋から冬にかけての期間なら、という条件です」と、言ってくれた。冬は雪が深く、寒いので戸外でのマーケットはやらないから、その期間は彼女は比較的時間があるのだという。
彼女の名前は、ローリー・プライブルといって、私と同年齢くらいで、手づくりのパンやケーキをレストランに卸したり、同時に個人のお客さんの電話での注文に応じてパンやケーキを作っている。まさに地域に根差したベーカリーだった。住まいのすぐそばに工房をもって、彼女は毎日そこで黙々と働く“職人”だった。
やがて、冬が近づきキャンパス内のマーケットはなくなり、ELSに通っていた私は毎水曜日になると、ケーキを習いにプライブル先生の店に通っていった。